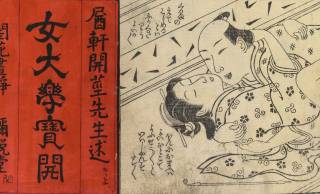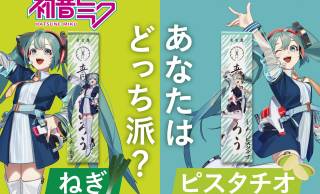- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由
- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由
- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

純喫茶の”純”っていったい何が純なの?カフェと喫茶店の違いも紹介します!:2ページ目
2ページ目: 1 2
「純喫茶」の”純”って何?
さて、喫茶店の看板にときどき「純喫茶」と出ていることがありますが、この「純喫茶」の“純”って何なのでしょうか。気になりませんか?この“純”の意味も説明しておきます。
もともと「純喫茶」とは、酒類を扱わない、純粋な喫茶店のことをいいます。昭和初期になると、酒類を扱い、女給による接客を伴う喫茶店が登場し、人気を博していた時期がありました。
昭和初期を舞台にしたドラマに「私、カフェで女給やってるの」なんていう女性が登場することがあります。こうしたお店のことを「特殊喫茶店」と呼び、それに対して、コーヒーや名曲を売り物にした本来の意味の喫茶店が「うちは純粋な喫茶店です!」という意味を込めて、「純喫茶」とわざわざ名乗るようになりました。
高井尚之さんの書いた『カフェと日本人』によれば、現在日本国内にあるカフェの店舗数は70454店もあるそうで、これはコンビニの数の1.4倍もするそうです。こうしてみると、いかに日本人が「お茶をする」習慣が定着しているのか、よくわかります。
そういえば、日本での喫茶の風習は、少なくとも鎌倉時代までさかのぼりますし、世界で最初の缶コーヒーやインスタントコーヒーを作った人も、日本人でしたね。
特許問題、資金不足…日本人によって発明された世界初のインスタントコーヒーと缶コーヒーのその後
一杯のカップになみなみと注がれたコーヒー。黒く輝くその不思議な飲料は、わたしたちの眠気を覚まし、元気にしてくれます。現在、私たちはそんな美味しいコーヒーを、インスタントや缶で、気軽に楽しめることができ…
多くの日本人に愛され、日本文化の中にうまく定着しているカフェ文化。今後もどのような進化をしていくのでしょうか。目が離せません。
参考
ページ: 1 2
バックナンバー
- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由
- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由
- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる
- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった
- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】