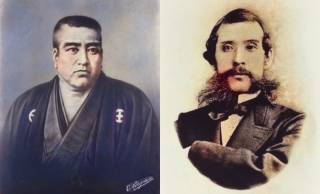なぜ日本人は頭を下げる?「お辞儀」に込められた日本文化の価値観や精神性とは……
日本を訪れた外国人の多くが、日本人があらゆる場面で「お辞儀」をしていることに驚きます。あいさつや感謝、謝罪、お願いなど、日常のあらゆる場面で、日本人は自然と頭を下げています。それは単なる習慣ではなく、日本人の価値観や精神性と深く関わっている行動です。
そもそも、人はなぜ頭を下げるのでしょうか。「お辞儀」は何を意味し、どのような気持ちを伝えているのでしょうか。
※合わせて読みたい記事↓
「なんで日本語ってはっきりしないの?」その理由を日本文化から考えると、日本語がもっと好きになる!
お辞儀は安心と信頼の合図
お辞儀の本来の意味は、「相手に対して敵意がないこと、こちらは無防備であること」を示す動作だったと考えられています。つまり、身をかがめて視線を下げ、相手に対して心を開くという行為です。そこに込められていたのは、安心と信頼の合図でした。
現代ではこの意味が広がり、「敬意」「感謝」「謝罪」「謙虚さ」など、さまざまな感情や社会的な配慮を伝えるための所作として受け継がれています。相手の立場を尊重し、自分の感情をおさえて調和を大事にする――そこに日本人の精神性が表れているのです。
お辞儀は、ただ形式的な動作ではありません。相手に心を向け、自分を一歩引いて礼を示すことで、場の空気が和らぎ、人と人との関係がなめらかになります。
だからこそ、日本人は無意識のうちに、電話口やメールの送信前にも自然と頭を下げることがあります。それは言葉を超えた“心の動き”が、身体に現れているとも言えるでしょう。
お辞儀の歴史
お辞儀の歴史をたどると、古代の日本にも頭を下げる文化がすでにあったことがわかります。『魏志倭人伝』には、身分の低い者が貴人と道で出会うと、地面にひざまずいて礼をしたという記述があり、これが現在の土下座のような礼法にあたります。
飛鳥時代から奈良時代には、中国から伝わった「立礼(りつれい)」が宮中儀礼に取り入れられ、しだいに日本固有の形式へと発展していきました。さらに、天武天皇の時代には、ひざまずいて地面に手をつく礼が禁じられ、立ったまま行う礼が奨励されたとも言われています。
この政策により、現代のように「立った姿勢で行うお辞儀」が制度として整えられ、広まっていったと考えられます。