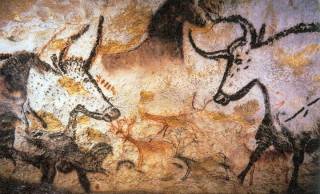箸墓古墳は”卑弥呼の墓”で決まりか?日本最大・最古クラスの古墳の秘密に最新学説が迫る【前編】
箸墓古墳の特徴
古代の大きな墳丘を持つ墓を古墳といい、古墳が築かれた時代を古墳時代と呼びます。古墳は全国各地で築かれましたが、なかでも奈良県桜井市には多くの古墳が集まっています。
その桜井市の数ある古墳の代表ともいうべき古墳が、箸墓古墳(はしはかこふん)です。
この箸墓古墳は日本最古の大型前方後円墳で、全長約280メートル。古墳時代前期の出現期の古墳のなかでは最大規模を誇ります。
本稿では、この箸墓古墳に眠る人物の正体について前編・後編に分けて説明しましょう。実はこの古墳は、かの卑弥呼のものであるという説があり、論争が続いているのです。
被葬者の候補
皇室に関わる古墳を管理している宮内庁によると、古墳の石室に眠るのは第7代天皇の孝霊天皇の皇女「倭迹迹日百襲姫」だということです(ちなみに倭迹迹日百襲姫は「やまとととひももそひめのみこと」「やまとととびももそひめのみこと」と読みます)。
しかしその確たる証拠はなく、被葬者は別の人物と見る専門家や研究者は少なくありません。
そこで、邪馬台国の所在地をめぐる論争のなかで畿内説を取る立場の人の多くは、箸墓古墳の被葬者を邪馬台国の女王・卑弥呼であると主張しますが、九州説の専門家や研究者をはじめ反対の立場の人もいます。
その反対理由のひとつが、卑弥呼が没した年代と箸墓古墳が築かれた年代との関係です。
ページ: 1 2