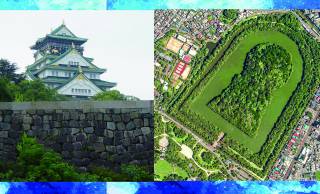人々の切実な願望を祈願した象徴「陰陽石」とは?奈良・水谷神社の「子授石」についての考察【後編】
古来より信仰の対象として祀られていた「陰陽石」は、人々の生活と密接し、その切実な願望を祈願した男女の陰部を象った自然石です。
人々の切実な願望を祈願した象徴「陰陽石」とは?奈良・水谷神社の「子授石」についての考察【前編】
読者の皆さんは、「陰陽石」というものをご存じでしょうか。簡単に言えば、男女の陰部に似た形の自然石のことを指します。今回は、奈良県内でも有数の人気を誇る春日大社の摂社「水谷(みずや)神社」にある…
【後編】では、「水谷(みずや)神社」の紹介と、そこにある陰陽石について考察しましょう。
古来より病気平癒・子授けに御神徳がある神社
「水谷神社」は、聖流とされる水谷川沿いに鎮座し、素盞鳴命(スサノオノミコト)・大巳貴命(オオアナムチノミコト)・奇稲田姫(クシナダヒメ)を祭神として祀り、上水谷・中水谷・下水谷三社においては下社に相当します。
同社は、平安時代から幕末までの神仏習合時代は、祇園精舎の守護神で医薬の神として尊崇される牛頭天王(ごずてんのう)を祀っていました。古くより霊験あらたかな神様として名高く、今も病気平癒や子授けを熱心に祈る人がみられます。
祇園精舎とは、釈迦が説法を行った場所で、その守護神・牛頭天王は別名・祇園天神と呼ばれ、有名な京都の八坂神社は幕末まで祇園社と称していました。
明治維新を迎え、政府による神仏分離政策により、同じ疫病除けの神ということで、牛頭天王と習合していた素盞鳴命に祭神が変更されたのです。
「水谷神社」の例祭は、毎年4月5日に行われる鎮花祭です。この季節は、桜の開花の季節に当たり、牛頭天王の御神徳である疫病流行を鎮める祈りをこめて斎行されます。
祭の当日は神前に桜の花を献じ、神楽が奉納されとともに、午後からは祢宜座狂言も演じられ、普段は静かな同社も多くの参拝客で賑わうのです。
ページ: 1 2