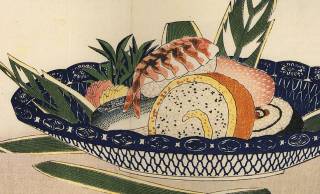江戸時代の経済を支えた両替商と「銀座」の意外な関係に迫る!
「銀座」の由来
江戸時代、銀貨幣鋳造所は「銀座役所」と呼ばれており、「銀座」とはこうした鋳造所のことを指していました。
関連記事:
「銀座」の本当の意味は?「金座」もあるって本当?地方都市に「〇〇銀座」が多い理由も探る
銀貨幣の鋳造所が「銀座」「銀座」という地名は、東京のあの地域を示すものとして有名で、日本全国にも「○○銀座」がたくさんありますね。そのため、銀座という言葉の元々の由来を忘れがちですが、実は…
銀座は、江戸・駿府・佐渡・京都の四か所にあった金座と違って幕府直轄の貨幣鋳造所ではなく、幕府から許可されて銀貨の鋳造を行っていました。
1598(慶長3)年、家康が京都の伏見に銀座を設け、堺の南鐐座から銀の精錬技術にすぐれた湯浅作兵衛常是を招いたことから「銀座」の歴史は始まります。
銀座は、伏見・京都・大坂・長崎・駿府・江戸などに設けられましたが、直接製造にかかわっていたのは江戸と京都だけで、1800(寛政12)年からは江戸に統合されました。
江戸の銀座は現在の東京都中央区銀座二丁目のあたりで、明治時代に鉄道の起点となった新橋と、江戸の経済の中心地であった日本橋を結ぶ位置にありました。
そのため銀座通りはにぎわい、「銀座」という言葉は繁華街の代名詞となったのです。
銭貨を鋳造する銭座も各地に設けられていましたが、多くは1700年代後半に廃止されました。現在も静岡市や長崎市などに銭座町という地名が残っています。