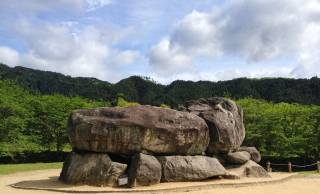最澄の天台宗、空海の真言宗…日本の仏教を変えた「密教」はその後どのように展開した?:2ページ目
2ページ目: 1 2
平安時代中期、天台宗は分裂します。比叡山延暦寺を中心とする円仁(えんにん)の「山門派(さんもんは)」と、園城寺(おんじょうじ)を中心とする円珍(えんちん)の「寺門派(じもんは)」が対立するようになりました。
この対立は、僧侶同士の議論だけでは収まらず、やがて僧兵(そうへい)を使った武力衝突に発展しました。
特に、山門派の僧兵は圧倒的な力を持ち、たびたび園城寺を焼き討ちしました。これにより、寺門派は延暦寺を追われ、園城寺を拠点としました。この争いは、平安時代末期には貴族や武士の政治争いにも影響を与えました。
山門派は源氏に、寺門派は平氏に味方するなど、仏教界が政治に深く関わるようになりました。
鎌倉時代に入ると、天台宗は他の新しい仏教宗派の影響を受けながらも存続します。一方で、山門派と寺門派の争いは続き、中世には南北朝時代の政争にも巻き込まれました。さらに、両派の僧兵たちは各地で争いを繰り広げました。
近代になると、天台宗は再編されました。1945年、宗教団体法の廃止をきっかけに、寺門派は「天台寺門宗(てんだいじもんしゅう)」として独立し、現在に至ります。
天台宗の歴史は、宗教の変化や分裂、そして争いを通して日本の歴史と深く結びついています。最澄がもたらした仏教の教えは、時代を超えて今も人々に影響を与え続けています。
参考
- 『インド中国日本 仏教通史 』平川彰(1977 吉川弘文館)
- 『日本仏教の礎』末木文美士(2010 講談社学術文庫)
- 天台寺門宗公式Webサイト
ページ: 1 2