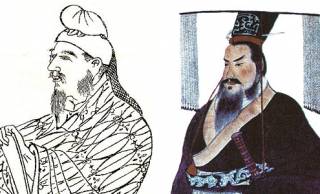推古天皇は“日本で最初の女性天皇“ではない!?日本最古の歴史書から読み解く知られざる女帝の系譜【前編】:2ページ目
二つの史料の記述
推古天皇が日本最初の女帝(女性天皇)であることは多くの文献に記されていますが、実は、推古天皇以前に女帝すなわち女性天皇がいたという説もあります。
その根拠は、『日本書紀』にある次のような記述です。
第2代の清寧天皇が崩御したあと、皇太子の億計王と弟の弘計王が互いに天皇の位を譲り合って、長い間、どちらも皇位につこうとしませんでした。
そこで、2人の姉である飯豊青皇女が忍海角刺宮で政治をみて、自ら忍海飯豊青尊と名のったといいます。
彼女が清寧天皇のあと政治をみていたことは『古事記』にも記されていますが、不思議なことに『古事記』と『日本書紀』の内容は異なります。
『日本書紀』によると、清寧天皇が崩御したあと2人の王がいたことになっていますが、『古事記』の伝えるところでは、清寧天皇が崩御したあとは天皇には皇后も皇子もなく、天下を治める王がいなかったというのです。
2つの所伝を読んだとき、どちらが当時の状況を正しく伝えていると感じるでしょうか。
『日本書紀』はいまひとつ緊張感に欠けますが、『古事記』に記された状況であれば皇統が途絶えるおそれがあり、天皇家はさぞかし慌てたに違いありません。
『日本書紀』に従えば、飯豊青皇女の執政は後の「称制」(天皇の死後、皇太子や皇后が即位しないで政務を行うこと)のようでもあり、あくまでも次の天皇が決まるまでの「つなぎ」くらいの感じです。
ところが『古事記』に従えば、飯豊青皇女はすなわち天皇不在という政治的空白の危機的状況を救ったわけであり、実質的な天皇と見ることもできそうです。
このあたりの解釈については、【後編】で詳しくみていきましょう。
【後編】の記事はこちら
推古天皇は“日本で最初の女性天皇“ではない!?日本最古の歴史書から読み解く知られざる女帝の系譜【後編】
参考資料:日本歴史楽会『あなたの歴史知識はもう古い! 変わる日本史』宝島社(2014/8/20)
画像:photoAC,Wikipedia