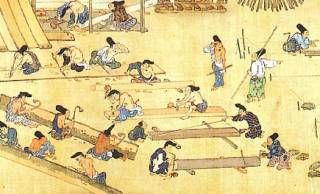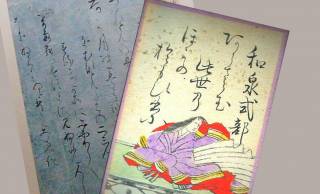蘇我馬子、小野妹子…なぜ男なのに「子」?なぜ動物の名前?古代日本の人名の不思議を解き明かす
なぜ動物の名前?
古代日本の人名は、現代から見ると「なんでこんな名前なの?」と理解に苦しむものがありますね。
古代の戸籍をみると、刀良売(とらめ)、比都自(ひつじ)などのように、男女とも動物にちなんだ名前が多く見られます。
例えば七〇二年(大宝二)の北九州言葉では、登録者の半分が動物にちなむ名前だったといいます。
歴史上の有名人でも、例えば蘇我氏の蝦夷・馬子・入鹿などがありますね。馬と鹿はいうまでもありませんが、蝦はエビのことです。
これは、干支にちなんで名づけられることが多かったからとみられています。
例えば、七二一年(養老五)の大嶋郷(千葉県)の二五戸分の戸籍をみると孔王部刀良売という名前の人が六人もいるのですが、当時、日本にトラは棲息していませんでした。
つまり刀良(トラ)という言葉は実際の動物のイメージからつけたものではなく、十二支という漢字文化の知識が名前に取り入れられた結果なのでしょう。
また、当時の暮らしは、自然が現代よりもはるかに身近にあり、動物とのかかわりも深かったと考えられています。そんなこともあって、人名に自然と動物名を使うことになったようです。
先に蘇我氏の例を挙げましたが、他にも熊鷲、熊、小熊、斑鳩、熊鷲、猿、羊、駒、犬養、鷹養、牛養、鯨、受験受岐、鯖麻呂といった名前も古代には存在していました。
ページ: 1 2