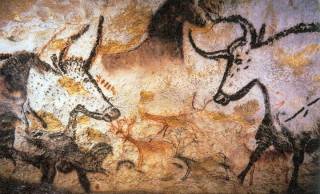「財閥」のルーツは戦国時代の”御用商人”にあった!彼らはどのように財をなしていったのか?
戦国武将と商人
戦国時代も後半になると、大大名は何万という家臣や部下を抱えていました。いざ、合戦になれば、その何万もの兵士たちに、十分な食料や日常品を与えなければなりません。
もちろん、大量の武器や弾薬も調達する必要があります。
しかも、戦いに間に合わせるために短期間で調達するには、専門の納入業者に頼らざるを得ませんでした。そうかといって、見ず知らずの業者に頼ればだまされる危険もあります。
そこで戦国武将は、気心が知れ、少々の無理を聞いてくれる商人たちとだけ取引するようになっていきます。
こうして、いわゆる御用商人が誕生しました。
御用商人は、戦国大名の需要に応じた物資の調達や人夫の調達にあたる特定の商人のことを指します。彼らは、時には他国の情報収集などにもあたることがありました。
これに対して大名側も、商人司などの役職につけて国内の商人の統制を行わせています。
たとえば、武田軍にとっての酒田氏、上杉軍にとっての蔵田氏、今川軍にとっての友野・松木の両氏などは、いずれも戦国大名の御用商人として財を成していきました。
「政商」のルーツ
徳川家康も、三河国を支配していた時代から御用商人を持っていました。
特に、江戸幕府成立後に公儀呉服師に任じられることになる呉服商は、単に呉服を扱うだけではありませんでいた。
彼らは兵粮や武具などの軍需物資の確保と輸送・対外交渉など幅広い分野で活躍し、時には家康・秀忠などの当主に近侍して戦場に立つ場合もあったとか。
これが、さらに時代が下ると政商(せいしょう)と呼ばれるようになります。
政商は、広義には政府つまり政治家や官僚とのコネ・癒着により、優位に事業を進めた事業家、あるいは企業グループのことを指します。
戦前日本の財閥はその代表例でといえるでしょう。
ページ: 1 2