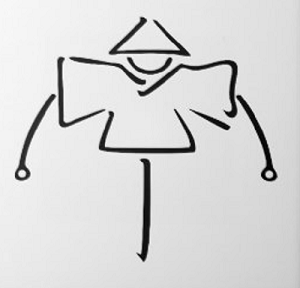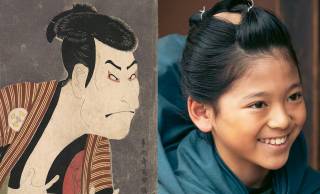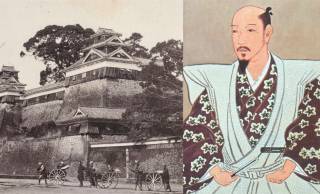- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった
- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】
- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】

弥次郎兵衛(やじろべゑ)人形の語源、実は「東海道中膝栗毛」の主人公から:2ページ目
与次郎、豆蔵、正直正兵衛……他にも色んな呼び方が!
ただし、この弥次郎兵衛という名称は江戸の地方名(方言)であり、全国的には釣合(つりあい)人形とか与次郎(よじろう)人形、笠人形とか水くみ人形、豆蔵(まめぞう)などと呼ばれているそうです。
【釣合人形】
釣合人形とは両腕の釣合(バランス)をとろうと揺れる様子を表したものであり、何とか真っ直ぐに立とうと頑張っているようにも見えることから、又の名を「正直正兵衛(しょうじきしょうべゑ)」とも呼ばれるそうです。
【与次郎人形】
与次郎(与二郎)とはそういう名前の物乞いが、門付(かどづけ)にこの人形を用いたことに由来するそうです。
ちなみに門付とは他人の門前で芸を見せて金銭や酒食を求める「大道芸の押し売り」みたいな生業で、現代でもお正月の獅子舞などにその名残が見られますね。
後に弥次郎兵衛と融合したのか、与次郎兵衛(よじろべゑ)と呼ばれることもあります。
【笠人形】
笠人形とはこうした物乞いたちが顔を隠すために深い笠をかぶったこと、あるいは人形にも自分たちを模して小さな笠をかぶせたことなどに由来します。
【豆蔵】
延宝~元禄年間(1673~1704年)ごろ、摂津国(現:大阪府北西部と兵庫県南東部)で活躍していた大道芸人の名前で、怪力を活かして身体を張ったパフォーマンスや、滑稽な話芸で人気を博したことから、後に大道芸人全般を指すようになったそうです。
彼らの愉快な動きが釣合人形に通じるため、そのネーミングとして定着したのでしょう。
ちなみに豆蔵は家紋のデザインとしても取り入れられて「一つ豆蔵」「豆蔵の丸」「豆蔵菱」「丸に豆蔵桐」「一筆豆蔵」など、ユーモラスな意匠が現代に伝わっています。
3ページ目 終わりに
バックナンバー
- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった
- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】
- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】
- No.193一番槍、抜け駆け などなど…現代でも使われている”武士の文化”に由来する言葉をご紹介
- No.192かつては”幻の豆”と呼ばれていた山形名物「だだちゃ豆」はなぜ ”だだちゃ” と呼ぶの?