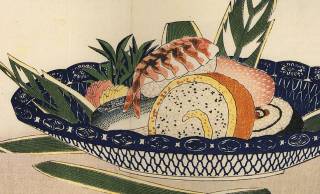- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由
- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由
- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

元ネタは逆さ吊りの刑?古代インドから来た「お盆」と言う名の由来とお盆の起源:2ページ目
2ページ目: 1 2
元ネタは逆さ吊りの刑?親子愛が生んだお盆の起源

お盆の正式名称は『盂蘭盆会』と言いますが、その語源は古代インドの言葉で『逆さ吊り』と言う恐ろし気な意味を持ちます。その起源については、以下のような話が伝わっています。お釈迦様に仕える弟子である目連尊者が亡くなった母の姿を探すと、生前の罪が原因で餓鬼道と言う地獄に墜ちていました。
餓鬼道は強欲や物惜しみをした人が行く地獄で、飲食物を得られずに苦しむため、目連は得意の神通力で食べ物を母に与えますが、全て火になってしまいます。亡母を哀れんだ目連の訴えを聞いたお釈迦様は、
「餓鬼道に落ちた亡者を救いたいならば、夏安居(げあんご。夏の修業期間)が終わった僧らに施しをするのです。そうすれば、その施しが、そなたの母上にも与えられようぞ」
と助言を与えます。
法会の宴に招かれた僧侶達の喜びは地獄界に伝わり、目連の母も飲食物を口にしてようやく救われ、最終的には成仏して天に召されていきました。目連がお釈迦様の助言で僧達に飲食物を振る舞い、かつ地獄の亡者にも供養をした神話が、今も日本各地のお寺に伝わる施餓鬼の起源説話です。
また、目連の母(もしくは目連本人か衆生)が救われたのを喜んで舞ったのが盆踊りの起源だとする説もあります。これは少し飛躍している感が否めませんが、亡き人を偲ぶ日にふさわしい物語であることに変わりはありませんね。
ページ: 1 2
バックナンバー
- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由
- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由
- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる
- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった
- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】