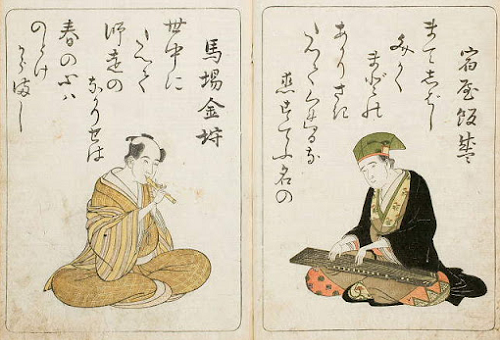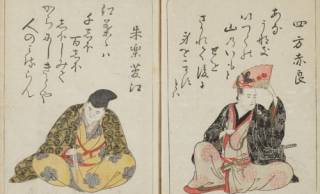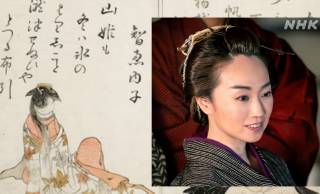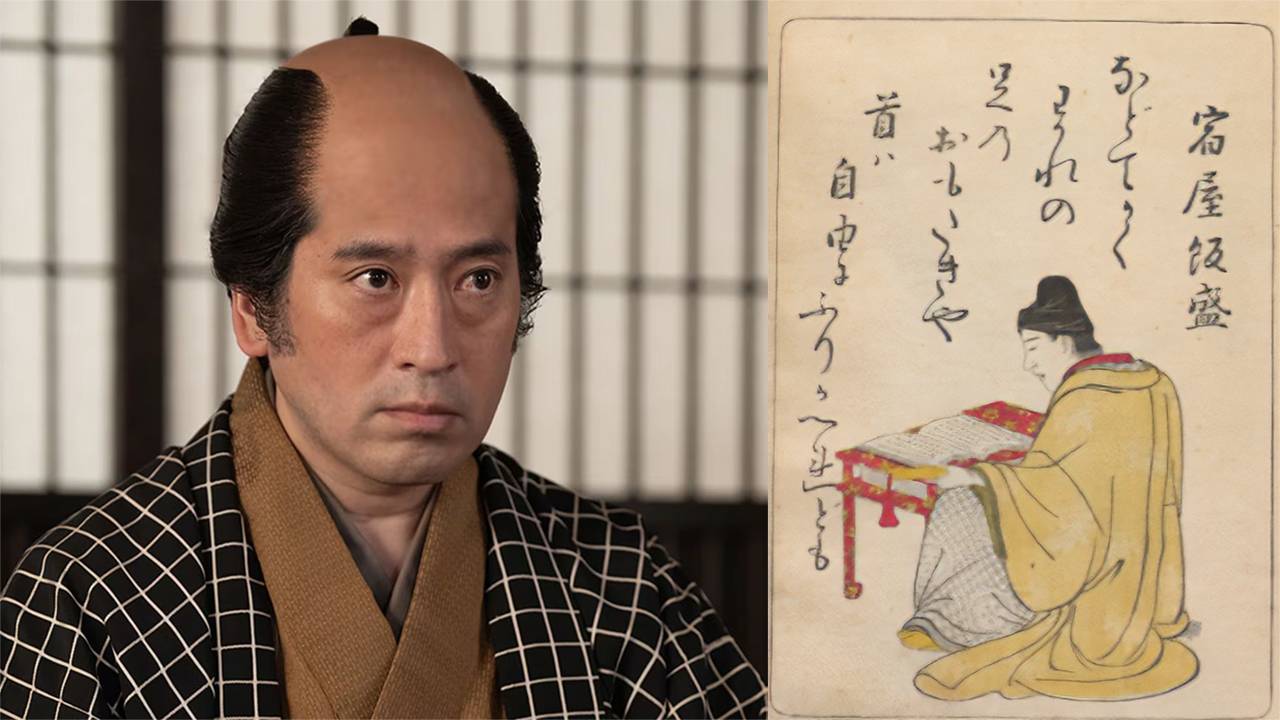
【べらぼう】で又吉直樹が演じる狂歌四天王・宿屋飯盛 〜遊女名を冠した男の素顔と復活劇
大田南畝に学び、狂歌四天王の一人に数えられた狂歌師
宿屋飯盛(やどやのめしもり)日本橋で宿屋を営んでいたことが狂名の由来とされる。狂歌集の編集・出版で蔦重(横浜流星)と協力し、天明8年には、歌麿(染谷将太)とともに狂歌絵本『画本虫撰(えほんむしえらみ)』を刊行し、狂歌師の地位を不動のものにした。蔦重が亡くなった後、蔦重の墓に碑文を残す。
※NHK公式サイトより。
天明狂歌ブームで多くの狂歌師が活躍した中で、特に優れた4人が狂歌四天王と称されました。
- 鹿都部真顔(しかつべの まがお)
- 銭屋金埒(ぜにやの きんらち)
- 頭光(つぶりの ひかる)
そして今回紹介する宿屋飯盛。果たしてどんな人物だったのか、その生涯をたどってみましょう。
※鹿津部真顔についてはこちらで紹介!
江戸時代に「狂歌四天王」として活躍した鹿津部真顔とはどんな人物だったのか?【大河べらぼう】
宿屋飯盛の生い立ちと名乗り
宿屋飯盛は宝暦3年(1754年)12月14日に江戸で誕生しました。
父親は浮世絵師の石川豊信(いしかわ とよのぶ)。父が旅籠屋(宿屋)を営んでいたことが、後に狂号の由来となります。
本名は糠屋七兵衛(ぬかや しちべゑ)、後に石川五郎兵衛(ごろべゑ)に改めました。
他にも彼は様々な名乗りを用いており、字は子相(しそう)、雅号に六樹園(ろくじゅえん)・五老山人(ごろうさんじん)・逆旅主人(げきりょしゅじん)・蛾術斎(がじゅつさい)など。
※字(あざな)とは中国大陸で、成人男性が実名に代えて用いた通称。当時は中国文化がインテリとされていました。
そして国学者としては石川雅望(まさもち)、狂歌師として宿屋飯盛を名乗ったのです。
ちなみに飯盛とは宿屋で働く非公認の遊女、飯盛女を表します。
関連記事:
飯盛女や湯女が遊女役。幕府公認「吉原遊郭」の強敵だった非公認遊郭「岡場所」とは?
それにしても、こんなにたくさんの名乗りがあって、使い分け切れていたのでしょうか。
※以下「宿屋飯盛」で統一します。
狂歌界の権威に
そんな宿屋飯盛は子供のころから利発だったようで、国学を津村綜庵(つむら そうあん)、漢学を古屋昔陽(ふるや せきよう)に学びました。
狂歌については頭光こと岸文笑(きし ぶんしょう)に学び、のち四方赤良(よもの あから。大田南畝)に学びます。
やがて狂歌の冴えで頭角を現すようになり、頭光たちと狂歌サークル「伯楽連(はくらくれん)」を結成しました。
宿屋飯盛の狂歌は『故混馬鹿集(ここんばかしゅう)』などに入選し、やがて蔦屋重三郎と組んで『古今狂歌袋(ここんきょうかぶくろ)』などの狂歌絵本を出版します。
こうした活動を通して狂歌界の権威を確立し、天明末期には狂歌四天王と称されるようになったのでした。
しかし寛政3年(1791年)には冤罪によって狂歌界から遠ざかってしまいます。