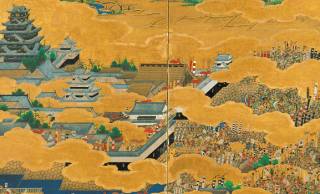鳴くまで待とう…などの徳川家康イメージは嘘だらけ!リアリスト・家康の真実の処世術と実像
人質時代も「国衆」として一定の権力
徳川家康といえば、今川・織田の両勢力に挟まれた三河の弱小領主の跡継ぎというイメージが根強くあります。
幼少期の大半を人質として過ごしたこともあり、そこから忍耐の人という人物像ができあがったのですが、実際には国衆の一人としての力を持っていたことが最近は分かってきました。
※関連記事:
怒り狂い刀を振り回す暴挙!?実は徳川家康の名君イメージは作られたものだった。その実像とは
家康といえば〈鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス〉という句が有名です。これは江戸時代に詠まれたもので、家康の性格を表すものとして知られています。
実際、家康の人物像と言えば今でもそんな感じですね。織田信長・豊臣秀吉の活躍に隠れつつ、時機が来るまで待ち続け、最後に天下を取った忍耐の人――。しかしこうした人物像は、徳川氏(松平氏)の始祖・家康を「神君」とあがめた幕府の記録によるもので、必ずしも真実とは言えません。
そうした記録には、将軍家を天下人として正統付けるための創作も多く含まれています。
こうした、いわば「松平・徳川中心史観」を排した実証的な研究が進んだのは1970年代以降のことです。近年は戦国時代の社会論などの研究成果も反映し、より実像に迫った家康像が描かれています。
従来と捉え方が変わってきている例の最たるものが、幼少期の「人質」時代でしょう。
今川・織田の両勢力に挟まれた三河(愛知県東部)の松平氏は、家の安泰のために今川義元へ庇護を求めました。そして家康(当時は竹千代)が数え8歳で今川領駿府(静岡市)に送られたのは、皆さんもご存じの通りです。
それ以降、10歳まで過ごした駿府時代の苦労が強調されることが多いですね。
しかし父の死後に松平家当主となっていた家康は、義元の支援を得つつ、自らの裁断に従うよう命じる「定(さだめ)」を本領である岡崎(愛知県岡崎市)の家臣に出すなど、駿府にいながら領国の運営にあたっていたのが実態でした。
このように、今川などの大大名に従属しつつ、小規模の地域を領国として運営する権力は「国衆」と呼ばれ、近年の戦国研究でも実態が明らかになりつつあります。
こうした観点でいけば、当時の家康もれっきとした国衆当主であり、「人質」という言葉にイメージされるような無力な存在ではなかったのです。