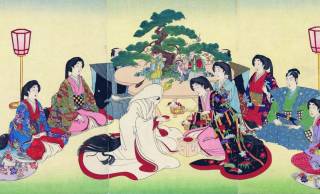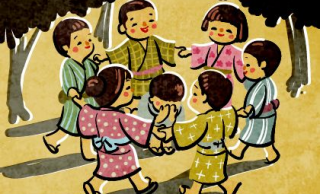寺子屋、駆け込み寺…信仰の場だけじゃない、”地域のインフラ”として機能したお寺が秘めるチカラ
皆さんは、お寺の境内と聞いて、何を思い浮かべますか?
静かに佇む本堂、手入れされた庭、遠くから聞こえる鐘の音。多くの人にとって、お寺は「祈りの場」「心を落ち着ける場所」として記憶されているかもしれません。
でも、少し立ち止まって見渡すと、そこには日本の歴史の中で、お寺が果たしてきた“もうひとつの役割”が見えてきます。
時代によって様々な役割を担ってきた日本の寺院のこれまでの変貌を紹介
「信仰の場」だけじゃない、地域のインフラとしての境内
日本の寺院は、古代から近世にかけて、信仰の場であると同時に、地域社会の中核を担ってきました。
奈良時代の官寺、平安・鎌倉期の密教寺院、戦国期の戦略的寺社、江戸時代の檀家制度——時代ごとに形を変えながらも、寺は常に地域とともにありました。
江戸時代、全国に普及した檀家制度により、寺は一人ひとりの戸籍管理や葬送儀礼の拠点となり、「どこの寺に属しているか」が、個人の社会的所属を示す目印にもなっていました。
出生、婚姻、死亡の記録が寺に集まり、人びとの人生と寺は、切っても切れない関係にあったのです。
子どもを育てた「寺子屋」としての顔
寺が果たしていたもうひとつの大きな役割が、教育です。
寺子屋と聞けば、板張りの教室で筆を持つ子どもたちの姿を思い浮かべるかもしれませんが、教えていたのは読み書きだけではありませんでした。
あいさつの仕方、礼儀作法、声の出し方や年長者との接し方など、社会で生きていくための“人としてのふるまい”が教えられていました。
こうした教育は、のちに「修身」として近代教育に引き継がれ、近代国家の形成にもつながっていく要素だったとも言えるでしょう。
江戸時代、全国に自然発生的に広まった「寺子屋」ではどんな勉強をしていたのか?
「駆け込み寺」は実在した
ドラマや小説で耳にする「駆け込み寺」。実はこれは、江戸時代の制度のひとつであり、女性が逃げ込めば夫との縁を切る手続きができる寺院が、実在していました。
寺に逃げるしかない!江戸時代、自ら離婚できない女性を救済した”縁切り寺”とも呼ばれた「駆け込み寺」の仕組み
また、寺では病人に薬草を施し、困窮者には食事を分け与えるなど、福祉の拠点としての機能も果たしてきました。
これは西洋における教会や修道院、イスラム圏のモスクやワクフと共通する点でもあります。宗教施設が地域の福祉や生活インフラとして機能していたのは、世界共通の現象ともいえるでしょう。