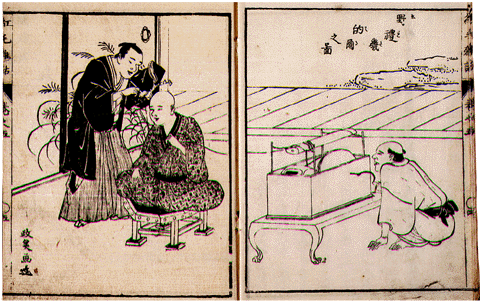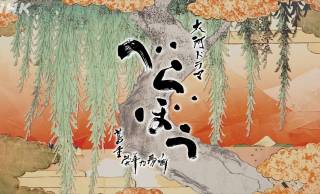大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【前編】:4ページ目
周囲を魅了する明るさや輝きの中に感じる繊細さ
才気煥発・軽妙洒脱・自由奔放に見える人柄や生き方は、周囲の人たちを魅了したのでしょう。支援する人々は多く、学者や文人、時の老中田沼意次(渡辺 謙)まで、華麗な人脈も築いています。
しがらみや立場、常識に縛られて生きる人が多いなか、源内の天衣無縫で時代の最先端を臆さずに進む行動力に「次に何をしでかしてくれるのだろう?」と期待をしつつ、見守っていたかもしれません。
常に新しいもの・珍しいものをもとめて、日本全国をかけ巡っていた源内は、ひらめきでさまざまな分野に手を付け熟慮せず、見切り発車的に進め大成しなかったことも多々あったようです。
破天荒にみえて繊細な源内は、人からの期待をひしひしと感じつつも「源内らしくない」と言われてしまいそうな、とどまる・熟考する・中止するなどが「引くに引けない」「カッコ悪くてできるか」という気持ちもあったのかもしれません。
「光」が強ければ強いほど、その分「影」も濃くなり「闇」は深まります。
さまざまなトラブルを抱えるようになった源内は、自分の作品が不評だったことに激怒したり、ちょっと尋常ではないような奇妙奇天烈な絵を描いたりなど、奇異な行動をするようになっていったとか。
ドラマの15回「死を呼ぶ手袋」では、「エレキテルの悪口」を耳にして町人に抜刀(竹光ですが)したりなど、徐々に闇に蝕まれてきたかのように見えるシーンもありました。
ドラマの登場人物(もちろん視聴者にも)に「夢」や「生き方」について、思わずハッとするような自然体の名言を与え続けてきた源内が、なぜ闇に落ちて行ったのか。
「生まれる時代が早過ぎた」「今の時代にいたら、さまざまな方面で偉業をなしとげただろう」と惜しむ声をよく聞きます。
封建的な時代の制約・認められない孤立感・経済的な困窮・うちなる葛藤・自分の中の光と影のコントラストの強さへの疲弊なのか……。
そして、なぜわざわざ“幽霊屋敷”に住んだのか……。
【後編】の記事はこちら↓