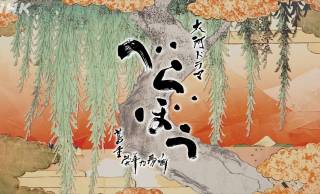大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【前編】:2ページ目
軽妙洒脱で頭の回転が速い人物
キャラクターとしては、安田顕さんが演じているように、実際、自他共に認める天才ぶりを否定しない自信満々な性格で、ある時は大風呂敷を広げ、人の意表をつくような奇想天外な発想を次々繰り出す、頭の回転が早い人物であったと伝わっています。
脚本でも源内は、賢く多才ぶりを発揮しつつもどこか子供っぽいおちゃめなところもあり、早口でどこまで本気かわからないような軽妙洒脱な話っぷりが特徴。時に調子がいいなという感じがあっても、憎めない人物です。
初回登場したときから、面白おかしいまさに“陽キャ”というイメージの源内。「日本におけるコピーライターのはしり」ともいわれ、ドラマの第2話「吉原細見『嗚呼御江戸』」では、歯磨き粉「瀬石膏」を売り出すときに「金に困って出したんで、効果があるかはわかんないけれど、ひとつ助けると思って買ってちょうだい!」という意表をついた広告で大ヒットさせた有名人として描かれていました。
そんな源内に吉原のガイドブックの序文を書いてもらおうと、吉原でもてなす蔦重。瀬川こと元・花の井花魁が、男色家の源内は恋人で亡くなった二代目瀬川菊之丞に想いが残っていることを察し、歌舞伎役者の男装姿で舞い、源内の思い出に寄り添う場面は印象的でした。
静かに恋人と過ごした時間を想い出しつつ涙を浮かべる源内の姿は、明るくてちょっとうさんくさい“陽キャ”とはまったく逆の、繊細でどこか孤独な影を纏っていました。
源内自らが発明した「金唐革紙」製の洒落た巾着
「べらぼう」で描かれる源内は、「キンキン先生」(吉原の通人、もしくは通人をきどるかっこつけているだけの人)が好んで真似していた、細い本多髷のような特徴的な髪型をしています。
そして、エキゾチックで派手な柄の着物や羽織を粋に着こなし、持ち歩いている巾着は「金唐革紙」製。
この「金唐革紙」は、江戸時代に海外から日本に渡ってきた美しい装飾用革で、革の凹凸をつけて金の箔押しを施し模様をつけたもの。幕府に献上された後に一般に広がり、刀の鞘やタバコ入れなどに用いられたそうです。
非常に高価な素材だった「金唐革」を、より手軽に大衆的にと「金唐革紙」を考案したのが平賀源内だったとか。源内が制作した金唐革紙製の「文箱」は源内直筆の書状とともに現代にも伝わっています。