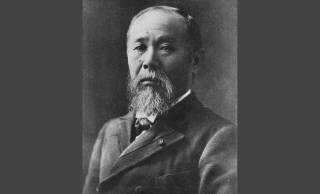なぜ日本は「憲法」を変えたのか?明治憲法から日本国憲法への変遷とその影響【前編】
昨今、「憲法」という言葉を聞くと、多くの人が現在の「日本国憲法」を思い浮かべるでしょう。ところが、日本にはかつて「大日本帝国憲法」という別の憲法が存在していました。
これは、1889年に明治政府によって制定され、1947年に日本国憲法が施行されるまで、日本の統治の基盤となっていたものです。
では、大日本帝国憲法はどのようにして作られ、どの国を参考にしたのでしょうか? そして、現代の憲法とはどのように違うのでしょうか?
今回は、日本の歴史を振り返りながら、憲法の変遷を考えてみましょう。
明治政府が憲法を作る必要があった理由
明治時代、日本は近代国家として発展するために、西洋の制度を積極的に取り入れました。特に、強い国を作るためには法律を整備し、憲法を持つことが不可欠だと考えられました。当時のヨーロッパ諸国ではすでに憲法を制定している国が多く、日本もそれに倣う必要があったのです。
では、どの国の憲法をモデルにするのか。フランスやイギリスの憲法も研究されましたが、最終的に日本政府が参考にしたのはドイツ(プロイセン)の憲法でした。その理由は、ドイツの憲法が「君主を中心とした強い国家体制」を持っており、日本の天皇制と相性が良かったからです。フランスやイギリスのような民主的な憲法は、当時の日本には馴染まないと判断されました。
ページ: 1 2