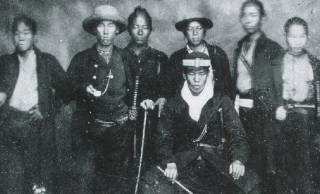教科書からすでに「士農工商」は削除!実は身分制度・身分序列を表す言葉ではなかった【前編】:2ページ目
古代にはあった!
士農工商という概念は古代から存在していました。もともとは中国から輸入された概念であり、少なくとも奈良時代には日本でも使われていたようです。
「士」という単語も、もともとは中国の貴族階級を指すものでしたが、17世紀までには武士を指すものとして、日本でも使われるようになっていました。
では江戸時代はどうでしょうか。ここでまず押さえておきたいのは、江戸時代は確かに身分制度・身分序列があったものの、それは意外と流動的なものだったということです。
例えば豊臣秀吉が農民から出世をして天下人になったように、もともと日本の身分制度は想像されているよりも自由なものであり、江戸時代もそれを受け継いでいたところがあったのです。
江戸時代の身分序列は、大まかに言えば「士」(武士)の下に「百姓」「町人」(平人)がおり、さらにその下に「穢多」「非人」(賤民)という身分があったというのが現代の考え方です。
ちなみに士農工商の「工」にあたる職人は、町に住んでいれば町人、村に住んでいれば百姓でした。百姓は農業従事者に限らず、海運業や手工業も含む概念でした。
百姓という言葉は文字通り「百の姓」で、戦国時代から近世初期にかけては農民だけを示す言葉ではなかったのです。