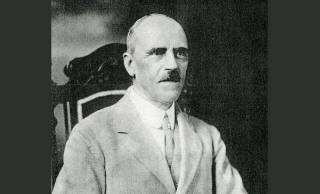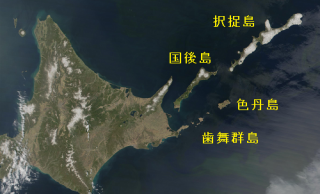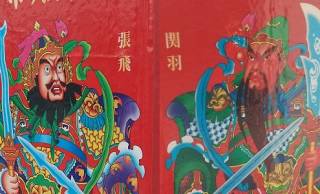神奈川県に護国神社を!創建前に横浜大空襲で焼失…幻の「神奈川県護国神社」とは?
幕末以来、日本の国難に殉じた英霊たちを祀る護国神社は、東京都と神奈川県を除く45道府県に存在しています。
東京には同じ趣旨の靖国神社が鎮座、全国の英霊をお祀りしているため、実質的に都道府県単位で英霊をお祀りしていないのは神奈川県だけと言えるでしょう。
日本の平和と独立を守るために戦い、尊い命を奉げられた英霊に対して、感謝の気持ちがないのでしょうか。
しかし神奈川県でも護国神社を創建する動きがないわけではありませんでした。
そこで今回は、神奈川県における護国神社創建の歴史をたどってみたいと思います。
神奈川県に、護国神社を!
神奈川県における護国神社創建の動きは昭和9年(1934年)、政府が一県に一社の護国神社を創建する方針を打ち出したことで始まりました。
当初は海軍鎮守府・軍港がある横須賀が注目されていたようですが、海軍と護国神社の縁は薄く、また神奈川県としては当初から県庁所在地の横浜を考えていたようです。
やがて昭和14年(1939年)4月に護国神社制度が正式に始まると、同年6月には神奈川県知事の号令によって神奈川県でも護国神社の創建運動が始まりました。
幕末に多くの殉難者を出した小田原や、大磯&平塚、そして横須賀など県内各地で大規模な誘致運動が展開されたと言います。
ただし神奈川県としては横浜に護国神社を創建する方針を崩さず、11月には護国神社の創建予算が成立し、翌12月には県議会で承認されました。
また11月28日には神奈川県護国神社創建会が設立され、用地選定や買収などを主導していくことになります。
神奈川県護国神社の予定地としては横浜市内の岸根(港北区)・下永谷(港南区)・野毛山(西区)・保土ヶ谷(保土ヶ谷区)・三ツ沢(神奈川区)がノミネートされ、昭和15年(1940年)に三ツ沢が選ばれたのでした。