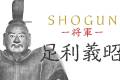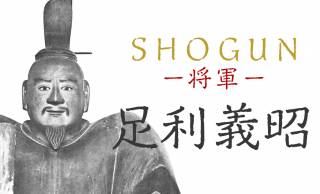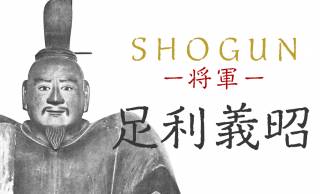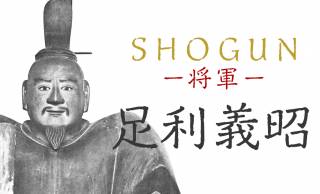名ばかり将軍たちの悲哀…室町幕府はなぜ ”ゆるブラック企業” 的な存在に?トップの無力ぶりを検証:2ページ目
2ページ目: 1 2
家臣が将軍を「すげ替える」時代に
室町幕府の後半では、将軍が力を持たずに“立てられる存在”となり、家臣たちの都合で将軍が交代させられる「すげ替え」が行われるようになります。
たとえば、十代将軍・義稙(よしたね)は何度も将軍の座から追われ、復帰してはまた追放されるという“リピート就任”すら経験しています。
極めつけは、十五代将軍・足利義昭。織田信長に担がれて将軍となりますが、のちに信長と対立し、京都から追放されてしまいます。
流浪と反逆!室町幕府のラスト将軍・足利義昭の苦難と悲劇に満ちた壮絶人生【前編】
皆さんは、ドラマ『SHOGUN将軍』、ご覧になられましたか? 日本での制作ではないにもかかわらず、その精緻な日本文化の再現度、徹底したリサーチに基づくリアルな描写、そして日本語がメインの脚本という特異…
この時点で、将軍職はもはや「実権あるリーダー」ではなく、「使えるかどうか」で価値を決められる道具のような扱いだったといえるでしょう。
形式と実態がズレた組織の末路
こうした将軍たちの姿は、現代における“役職だけが立派な社長”に重なる部分があります。肩書きはあるけれど、実際の決定権は部下が持っている。責任だけは残り、信頼や実行力がともなわない。
それが“ゆるブラック企業”的な組織体質だったとも言えるのではないでしょうか。
けれども、このような不安定な時代の中で、地方の武士たちは自ら動き出す力を育てていきます。こうして「下剋上」が進み、やがて戦国時代が幕を開けていくのです。
将軍が将軍でいられなかった時代の意味
室町幕府は、将軍という制度がありながら、将軍がリーダーシップを発揮できない時代でした。けれどもその矛盾と混乱のなかから、「リーダーとは何か」「名目と実態はどうあるべきか」という問いが浮かび上がります。
この時代の将軍たちをただ「無力だった」と見るのではなく、時代の流れや制度の限界を映し出した存在として見ると、歴史の見え方が変わってきます。
“肩書きがすべてではない”。そう語りかけてくるような、静かな重みが室町将軍の背中にはあったのかもしれません。
参考文献
- 呉座勇一 著『応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱』(2016年 中央公論新社)
- 山田徹(他)著『鎌倉幕府と室町幕府 最新研究でわかった実像』(2022年 光文社)
- 渡邊大門 編『諍いだらけの室町時代 戦国へ至る権力者たちの興亡』(2022年 柏書房)
ページ: 1 2