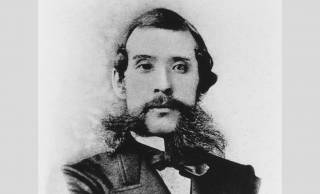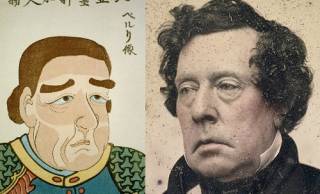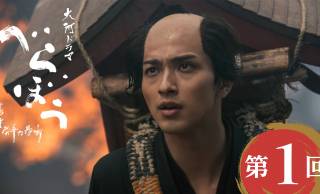賄賂政治家として知られる田沼意次の実像に迫る!従来の負のイメージが覆る驚愕の学説を紹介
賄賂で座敷がいっぱい
江戸時代中期の旗本、大名、江戸幕府老中、田沼意次(たぬまおきつぐ)という名は、長い間「賄賂政治家」「悪徳政治家」の代名詞のように伝えられてきました。では、実際には彼はどんな政治家だったのでしょうか。
関連記事:
どちらの財政政策も理にかなっていた。江戸時代の田沼意次の財政政策と松平定信の寛政の改革
資本(お金)があるから役人に給与を支払うことができ、それによって質の高い公共サービスを提供することができる。あるいは武器や兵器など、国防上必要なものに投資することができる…。政治の世界では国の…
従来のイメージを覆す説が、現在では定説となっているのです。
江戸時代中期の1719(享保4)年、意次は600石の旗本田沼意行の子として生まれ、家督を継いだ後は順調に昇進。その後、老中にまでのぼりつめて幕閣の実権を握りました。
実力者となった「田沼様」のもとには、その権力を頼って近づいてくる者が増えます。田沼屋敷には毎日、早朝から訪問客が列をなすようになったといいます。
客から預かった刀を置く部屋は、たくさんの刀で青海波(波形の染め模様)を描いたようになったという伝説まであります。
訪問客は刀だけ差してきたわけではなく、屋敷の廊下には小判のほかにも客からの贈答品がうず高く積まれていました。
また、ある時は、意次がイワセキショウという植物を観賞すると分かると、2、3日後にはあちらこちらからイワセキショウが贈られてきて2つの座敷がいっぱいになってしまったといいます。
もともと意次は、
「金銀は人の命に代えられないほどの宝なり。その宝を贈ってでも御奉公したいと願うほどの人であれば、志は忠であることは明らかです。その志の厚い薄いは贈り物の多少にあらわれる」
とも公言していたとか。そんな信念もあってのことでしょう、彼は自分が賄賂を使って出世したように、人の出世も賄賂によって世話をしたのでした。