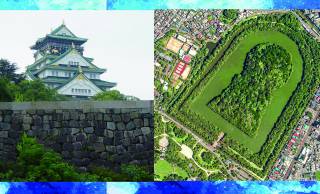豊臣家が滅ぼうとも大坂は衰退せず!大坂はいかにして「天下の台所」となったのか?:2ページ目
2ページ目: 1 2
こうして水運網が整備されると、諸藩は蔵米を保管し、換金するための蔵屋敷を堂島や天満、中之島などに設けるようになりました。そして、米以外にも麦や塩・砂糖・油など多くの物資が大坂に集積したため、商品の流通や金融に関わる問屋や両替商といった商人が集まるようになり、経済活動が活発化しました。
こうして大坂は物流取引の中心地となったのです。
「天下の台所」という言葉が使われ始めたのは、大正時代の歴史学者・幸田成友の頃からですが、諸藩の年貢米や産物の多くが、蔵屋敷に運びこまれ,商人たちの手で売り捌かれ、大消費地の江戸へ大量の物資が送りこまれた地域ということを考えると、元々様々な食材や用材をため込んだ部屋を意味する「台所」という言葉は、いい得て妙かもしれません。
参考
ページ: 1 2