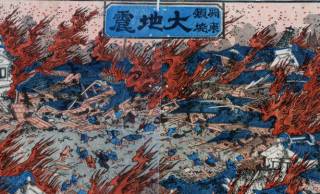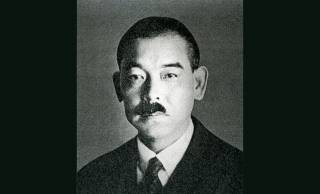まさかの”粘土の硬貨”!?戦時下の物資不足で日本の貨幣の素材は驚くほどコロコロ変わっていた
軍需物資に転用
国家総力戦となった近代の戦争では、膨大な金属を消費しました。その結果、日本では貨幣の原材料も次々に変わっていきました。その変遷をご紹介しましょう。
 戦時中に最も多く消費されたのは鉄でしたが、銅や亜鉛・アルミニウムなども軍需物資に転用されたため、戦争中は硬貨の原材料がたびたび変わります。
戦時中に最も多く消費されたのは鉄でしたが、銅や亜鉛・アルミニウムなども軍需物資に転用されたため、戦争中は硬貨の原材料がたびたび変わります。
1937(昭和12)年に日中戦争が始まり、戦時体制が強化されると、ニッケル製の10銭硬貨と5銭硬貨の製造が中止となります。
それにかわって翌年から製造されたのが、アルミニウム青銅製の10銭硬貨と5銭硬貨です。
このうち前者は銅が95%、アルミニウムが5%の合金でできていました。
その表面には菊の紋章と波があしらわれ、中央の穴を太陽に見立てて海の向こうから朝日が昇っている、いかにも戦時下に喜ばれそうなデザインでした。裏面には桜の花が描かれています。
純アルミニウム製が作られるも…
ところが、銅は電線や弾薬の雷管、弾丸などの軍需物資の製造に不可欠だったことから、昭和15(1940)年にはアルミニウム青銅製硬貨の発行も停止となります。
そして同年、純アルミニウム製の10銭硬貨と5銭硬貨が発行されました。
10銭硬貨の表面には菊の紋章、裏面には桜の花のモチーフ、5銭硬貨の表面には菊の紋章と吉兆を表す瑞雲、裏面には神武天皇の弓(弓の先端)にとまったとされる金色の鵄(金鵄)が描かれています。
発行当初1.5gあったアルミニウム製の10銭硬貨は、太平洋戦争がはじまる1941(昭和16)年には大きさはかわらずに薄くなって1.2g、1943年にはさらに薄くなって1.0gとなり、5銭硬貨も1.2g、1.0g、0.8gとどんどん軽くなっていきました。
そして、戦局が不利になってきた同年には発行が停止されてしまいます。回収されたアルミニウム製の貨幣のほとんどは、飛行機の原材料となったのでしょう。