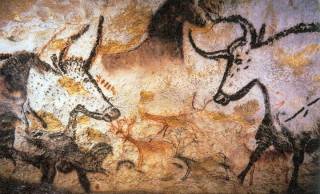弥生時代に見る農業技術のルーツ!日本では米作りが始まった当初から「田植え」は行われていた
「田植え」の証拠
弥生時代の日本の稲作に関する考古学の新発見に注目すると、現代の農業技術のルーツが見えてきます。古代の日本人がどのようにして稲作を発展させてきたのか、その秘密に迫ります。
日本の稲作は縄文晩期にはじまりました。戦前までの考古学では、縄文晩期から弥生時代にかけての稲作は、種籾を直接水田にまく直播きが主な農法で、田植えは行われていなかったと考えられていました。
ただし、それを裏付ける考古学的発見はなく、これはあくまでも直播きの方が簡単にできることからの推定でした。
ところが、戦後まもなく行われた静岡県の登呂遺跡の発掘調査以降、各地で水田跡が発見され、弥生時代にも田植えが行われていたことが明らかになりました。
たとえば、弥生末期の百間川遺跡(岡山県)の水田跡には坪当たり400株前後の稲株の跡が残っていました。しかもそれが規則的に配列されていたことから、田植えが行われていたことがうかがえるのです。
現在では、水稲耕作の初期段階から、直播きと田植えの両方が行われていたことがわかっています。
ページ: 1 2