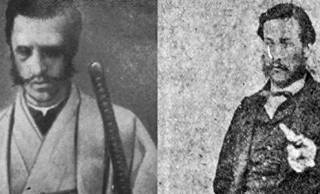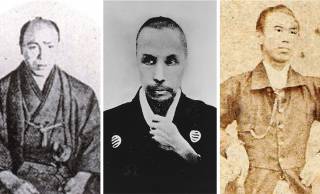なぜ太平の世・江戸時代に“鉄砲バブル”が巻き起こった!?江戸後期の武器ビジネスの実態【後編】:2ページ目
2ページ目: 1 2
現代的な営業努力
発見された文書群には、発注元の武家から送られた細かな注文書が多数残されていました。そこには鉄砲のサイズや銃身の文様といった各武家の要望が記され、鉄砲鍛冶は直接顧客とやりとりをしていたようです。
こうしたやり取りの中でオーダーメイドに応えられる技術力もあったようで、顧客を新規開拓したり、得意先をつなぎとめたりするために、井上家から武家に出された手紙も見つかっています。
これらの営業努力の内容からして、鉄砲鍛冶の間でも激しい競争があったことがよく分かりますね。
帳簿や取引先など、営業に関する大量の文書を蓄積することで、井上家は躍進できたのでしょう。現代で言えば取引先のデータベースを整備し、管理することで収益を上げていたのです。
もともと海外では軍事史の研究が盛んですが、近年は日本で作られていた火縄銃への関心も高まっています(特に戦国時代の日本は、世界史上でも最も鉄砲の生産が盛んだったとされており、世界一の軍事大国でもありました)。
よって、日本の銃砲史を更新させる貴重な史料は世界からも注目を集めるに違いありません。
参考資料:
中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)
画像:photoAC,Wikipedia
ページ: 1 2